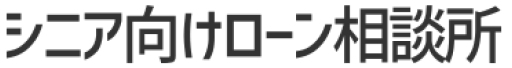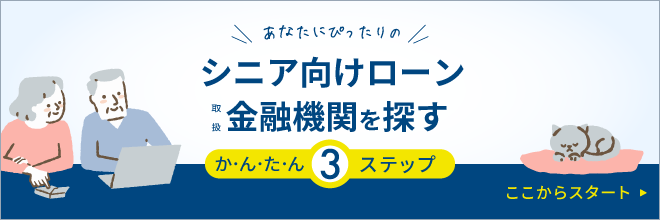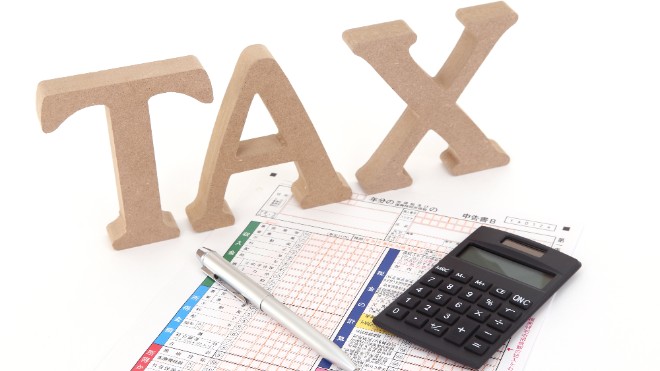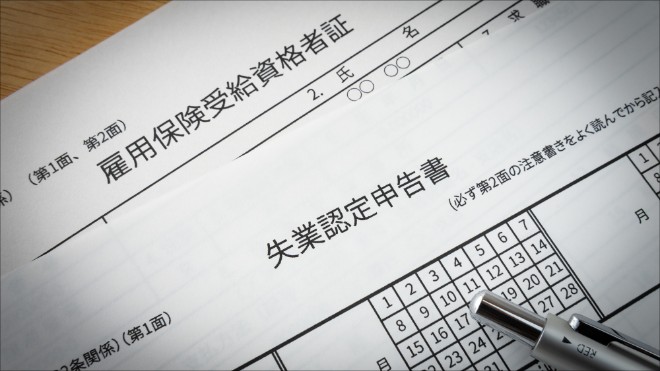公務員の退職手当は、一般企業に比べて多いのでしょうか。国家公務員と地方公務員の退職手当金額には、違いがあるのでしょうか。公務員の退職手当は勤続年や基本額、調整額によって決められます。物価が上昇している令和の世の中で定年を迎えつつあり、年金だけの暮らしに不安を感じている人のために、公務員や一般企業の退職金相場、計算方法、制度について解説します。最後には、老後資金の貯め方についてもご紹介します。
公務員の退職金制度
公務員の退職金制度は公表されており、国家公務員であれば「国家公務員退職手当法」、地方公務員なら各自治体条例を参照すれば退職金を計算することができます。たとえ勤続年数が1年であっても、定年退職と比べれば微額ではありますが、退職手当を受け取れます。
ただし、懲戒免職などの処分を受けたり、在職期間中に就業規則などに違反したため刑事事件に発展してしまったりした場合は、退職手当の全部あるいは一部が支給されません。支給後に非違行為が発覚した場合は、返納を求められることもあります。
公務員の定年は現行60歳ですが、定年の段階的引き上げが令和5年4月1日から始まり、最終的には令和13年度 に65歳まで引き上げられます。ただ、そうすると「60歳以後ではあるが、定年前に退職する人」も出てきてしまいます。しかし定年前に退職した場合でも、60歳以後であれば当面の間は定年退職と同様に退職手当が算定されます。
公務員の退職手当は、退職した翌月中には振り込まれます。
地方公務員・国家公務員の退職金相場
地方公務員の退職金相場
地方公務員の退職金相場を、都道府県職員の平均退職手当からみてみましょう。
【全都道府県職員の退職手当平均額】
|
|
全退職者の平均支給額 |
60歳定年退職者の平均支給額 |
|
全職種 |
1,374万円 |
2,204万円 |
|
一般行政職 |
1,210万円 |
2,148万円 |
|
教育公務員 |
1,479万円 |
2,230万円 |
|
警察職 |
1,663万円 |
2,199万円 |
参考:総務省「給与・定員等の調査結果等(令和4年)」から単位を「万円」に変え、小数点以下を四捨五入して作成
職種別では警察職の全退職者平均支給額がやや高いですが、定年退職者の平均支給額についてはどの職種においても2,200万円前後との結果が出ました。
国家公務員の退職金相場
国家公務員の退職金相場は、以下の通りです。
|
退職理由 |
常勤職員の平均支給額(万円) |
うち行政職俸給表(一)適用者の平均支給額(万円) |
|
計 |
1,061 |
1,442 |
|
定年 |
2,106 |
2,123 |
|
応募認定 |
2,541 |
2,279 |
|
自己都合 |
274 |
364 |
|
その他 |
200 |
230 |
※「その他」には、任期制自衛官等の任期終了(常勤職員)や死亡等による退職含む
参考:内閣官房内閣人事局「退職手当の支給状況(令和3年度)」から単位を「万円」に変え、小数点以下を四捨五入して作成
定年退職者の退職金平均額は、地方公務員と同様に2,000万円を超えています。また、応募認定退職においては、定年退職の退職金に少し上乗せされた金額が支給されていることがわかります。
公務員の退職金計算方法
国家公務員の退職手当は、以下の計算式で退職金が算出されます。
退職金=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給割合)+調整額
退職理由別・勤続期間別支給割合は、退職手当法により定められています。調整額は、在職期間中の貢献度に応じた加算額です。在職初日から末日までの各月ごとに、属していた職員の区分に応じて定められます。勤続9年以下の自己都合退職者等は調整額が支給されません。
参考:国家公務員退職手当法
大企業・中小企業の退職金相場
一般企業の退職金相場はどれほどなのでしょうか。大企業と中小企業に分けて解説します。
大企業の退職金相場
大企業の退職金相場は、中央労働委員会の調査によると、定年退職では約1,873万円、自己都合では約447万円という結果になりました。なかでもとくに高収入とみられる「男性・大学卒」の定年退職金相場は約2,230万円で、公務員と拮抗しています。
なお、同調査では「モデル退職金」も算出されています。「モデル退職金」は学校を卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進した場合に、職種別にどの程度の退職金が見込まれるかを表したものです。
大企業を定年退職した場合のモデル退職金は、以下の通りです。
|
職種、学歴、産業区分 |
定年退職した場合のモデル退職金(万円) |
|
事務・技術(総合職)大学卒・調査産業計 |
約2,564万円 |
|
製造業 |
約2,342万円 |
|
高校卒・調査産業系 |
約1,971万円 |
|
製造業 |
約1,875万円 |
|
生産 高校卒・調査産業計 |
約1,840万円 |
|
製造業 |
約1,824万円 |
参考:中央労働委員会「令和3年賃金事情等総合調査(確報)」
中小企業の退職金相場
中小企業の退職金相場については、東京都産業労働局のデータが参考になります。以下は、東京の中小企業に学校を卒業してすぐ入社した方が普通の能力と成績で勤務した場合の退職金水準です。
|
学歴 |
定年退職した場合のモデル退職金(万円) |
支給月数 |
|
高校卒 |
約994万円 |
23.2 |
|
高専・短大卒 |
約983万円 |
22.1 |
|
大学卒 |
約1,092万円 |
22.8 |
大学卒であっても、公務員や大企業社員の約半分程度の退職金であることがみてとれます。
老後資金の貯め方や準備
「老後は2,000万円の自己資金が必要」とよく報道されます。大きな金額に驚く人も多いでしょう。日々を慎ましく暮らせばそこまでの金額は必要ないかも知れませんが、家の修繕やリフォーム、老人ホームへの住み替え、病気やケガでの入院など、まとまった出費が必要になる事態は多くの人に訪れます。2,000万円という数字も、決して大げさなものではありません。
とはいえご紹介してきたように、公務員や大企業の社員でなければ2,000万円もの定年退職金は出ません。また、厚生労働省の「就労条件総合調査」をみると、退職金平均額は過去15年で700万円も下がっています。今後も退職金の金額は下がっていく可能性があります。
老後資金を準備する時期は、早ければ早いほどいいといえます。代表的な老後資金の貯め方や準備方法は、以下の通りです。
定期預金
今取引している銀行の窓口で、気楽に始められるのが定期預金です。最初に数年程度の受入期間を決め、期間中は基本的に引き出しができません。かわりに普通預金よりも金利が高く設定されています。通帳にある程度まとまった金額があり、しばらく引き出さないと分かっている場合は、検討してみましょう。
財形貯蓄
財形貯蓄とは、55歳以下の社員が勤務先と契約し、定期的に賃金からいくらかを引き落とすことで積立を行う制度です。目的を問わない使途自由な貯蓄である「一般財形貯蓄」、定年後に年金として受け取る「財形年金貯蓄」、マイホーム取得やリフォームのために積み立てる「財形住宅貯蓄」があります。老後の資金に不安がある人は、財形年金貯蓄制度が勤務先にないかどうか確認してみましょう。
企業型DC
DCとは「確定拠出年金」のことで、企業型DCは企業が毎月掛金を拠出(積み立て)してくれ、従業員が金融商品を選択したり資産配分を決めたりして運用する制度を指します。積み立ててきた資産は、退職一時金や年金の形式で受け取ることが可能です。
運用成績によって将来受け取れる退職金が変動します。もっと資産を増やしたい人は、企業が拠出する掛金に従業員自身が掛金をさらに上乗せする「マッチング拠出」が可能です。興味のある人は、制度が勤務先にないかどうか確認してみましょう。
iDeCo
iDeCoは「個人型DC」とも呼ばれ、企業ではなく自分自身が掛金を拠出して運用し、老後資金を作る年金制度です。60歳になった時点で10年以上の加入期間があれば、60歳から年金資産として積み立てた金額と運用益を受け取れます。請求時に、一時金か年金かを選択します。
ただし会社員や公務員の場合は掛金の上限が変動するため要注意です。自営業者等(第一号保険者)の場合は、国民年金基金と合算して月6万8,000円の拠出が可能ですが、会社員は最大で月2万3,000円までの拠出となります。
また、企業型DCに加入している場合は月2万円が上限で、確定給付企業年金に加入している場合は月1万2,000円が上限です。
iDeCoは、積み立てた掛金の全額が所得控除されます。本来であれば20%が税金となる運用益も非課税で、積立金を受け取るときは一時金として受け取るなら退職所得控除が、年金として受け取る場合は公的年金等控除を受けることができます。このように、iDeCoは税制上優遇されているのが特徴です。
NISA
NISAは少額投資非課税制度の愛称です。利用者は投資用として、NISA専用の口座を作ります。年間投資枠が定められたNISA口座内で金融商品を購入する限りにおいて、運用益が非課税になります。
これまでNISAは「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3つに分かれていましたが、2024年からは「つみたて投資枠」「成長投資枠」の2つになり、年間投資枠や非課税投資期間、非課税投資限度額などが抜本的に改正されます。これまでのNISAよりも投資枠が大きく、期限が長くなり、より使いやすくなることが期待されます。気になる方は、詳しく調べてみてはいかがでしょうか。

出典:金融庁「新しいNISA」
リバースモーゲージ
貯蓄や投資以外にリバースモーゲージという選択肢もあります。
リバースモーゲージは、自宅を担保に金融機関から融資を受けるもので、老後資金に悩むシニア向けの商品として近年注目を浴びています。自宅の評価額をもとに融資金額が決まり、契約者の存命中は利息だけを支払い、契約者が亡くなったら相続人が自宅を売却するなどして元金を返済します。
元金返済は契約者が亡くなってからになるため、契約者は安心して生涯を自宅で過ごせます。資金用途は投資などの目的でなければ自由なため、老後の家計を補填する他、家のリフォームやバリアフリー化でも利用できます。「誰も相続する予定のない自宅」がある人は、検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
公務員の退職金は、大企業の退職金と同程度の金額相場です。中小企業の退職金は、公務員や大企業の半額程度となります。定年が迫っている人だけでなく、若年層であっても老後に不安を感じている人やシニアライフの送り方に興味がある人は、自分の退職金がいくらになるか調べてみましょう。
もし調べてみた上で「老後資金が足りない」と感じたら、早めの対策がおすすめです。