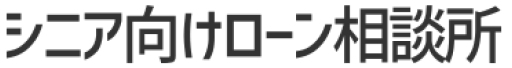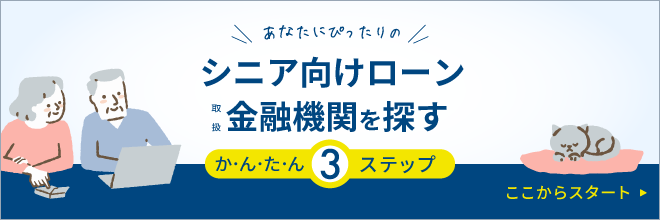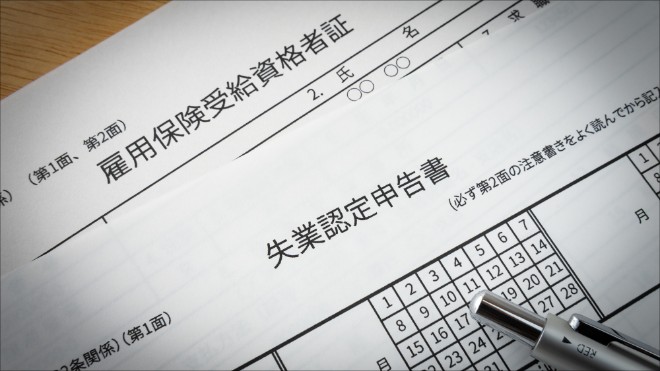原則としては、世帯全体の収入が最低生活費を下回ることで、生活保護を受けることが可能になります。生活保護を受けるべきかどうか迷っている人は、受給することによるメリットだけでなく、デメリットも気になることでしょう。地域によって違う受給額の実際も知りたいところです。生活保護の概要やメリット、デメリット、受給時の注意点について詳しく解説します。
生活保護とは
生活保護とは、生活が苦しい人も「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)を営めるよう必要な保護を行う制度です。足りない分の生活費を金銭の支給でサポートしてもらえるほか、病院にかかっても医療負担がなかったり、一部の税金を納めなくても良かったり、自立のための援助を受けることができたりします。
受給条件と申請方法を、順に詳しくご紹介します。
受給条件
生活保護の受給条件は、大き4つあります。
- 世帯単位の申請であること
- 資産を活用しても困窮していること
- 能力を活用しても最低生活費に届かない収入しかないこと
- 親族等から援助を受けることができないこと
まず、世帯員のうち誰かが最低生活費※を上回っていれば、受給することができません。そして、預貯金や生活に利用されていない不動産などの資産を売却しても、生活が困窮していることが求められます。
「能力を活用しても」とは、自分の能力を使って働いても、ということです。何らかの理由で働けない人も、これにあてはまります。また、親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けるべきとされています。
※最低生活費:厚生労働大臣の定める基準で計算される最低限の生活費のことで、地域により金額は違う。参考:最低生活費認定額(令和7年4月)
申請方法
生活保護の申請は、住んでいる地域を管轄している福祉事務所へ出向いて行います。担当者から生活保護制度の説明を受け、自分の近況について相談し、生活福祉資金の借入れなど他の制度の活用も検討しながら、どのようにすればよいかを担当者と一緒に考えます。
生活保護を申請したいという結論になったら、生活状況を把握するための実地調査として家庭訪問などが始まります。なお、預貯金や保険、不動産といった資産がどのくらいあるか、仕送りなどの支援ができる親族はいないか、もっと働くことはできないかなどの調査もあります。
申請から原則として14日以内に、生活保護を受けられるかどうかが決定し、書面で決定内容が送られてきます。
生活保護のデメリット
生活保護のデメリットは、主に以下の5点です。
収入があるとその分、支給額が減る
生活保護では、収入が最低生活費に満たなければ、満たない分だけが支給されます。よって、想定以上に働くことができたり、親族から仕送りがあったりしたときは、担当者に申告しなければなりません。そして収入が最低生活費を満たしている月には、受給ができません。
ローンの利用が制限される
生活保護費として支給されている金銭をローンに使うべきではないことから、生活保護を受けている間は新たなローンの利用が制限されます。ただし返済期間が短いローンや少額であれば利用可能な場合もあるため、相談が必要です。
家族に影響が出るかもしれない
お子さんがいる場合は特に家族への影響を慎重に見極めなければなりません。生活保護を受けていたら、お子さんが一生懸命アルバイトをして手にしたお金も「世帯収入」とみなされ、そのぶん保護費の受給ができなくなることもあるためです。
「子どもには自分が稼いだお金を自分のために使って、自立してほしい」と考えるなら、大学生になったときをめどに世帯分離をしたほうがよいかもしれません。同居していても世帯を分けることが可能です。
参考:進学する場合の生活保護制度上の取り扱いについて(長野県)
ただし、お子さんが義務教育中や高校在学中は、必要な学用品費や教材費が支給対象になるため、かえって助かる場合も多いです。お子さんの年齢によっては、ありがたい制度といえます。
プライバシーが制限される
生活保護を受けている間は、担当者が定期的に自宅を訪問し、生活調査を行います。その際、収入や支出についての報告をしなければならず、仕事がうまくいっているかどうかなどの質問にも答えなければなりません。担当者は調査に必要のない質問はしないため、無用なプライバシー侵害にはなりませんが、それでも抵抗がある人はいるかもしれません。
親族に受給のことを知られる
申請後の調査では、担当者が親族に仕送りができないかと連絡を取る「親族照会」があります。「親族になるべく迷惑をかけたくない」と考え、この親族照会があることを理由に申請をためらってしまうケースが多くみられるようです。
生活保護のメリット
生活保護のメリットは、主に以下の5点です。
金銭面での不安がなくなる
お金がないことによる精神的な辛さは相当なものです。生活保護を受け、最低限の生活が保障されると、とりあえず「明日を迎えられる」安心は手に入ります。病気療養中の人は治療に専念でき、家計のためアルバイトせざるを得なかった学生は、自身の勉強に専念できます。
担当者に悩みを相談できる
生活保護受給世帯になると、福祉事務所のケースワーカーが担当者としてつき、定期的に家庭を訪問してくれます。家計に関する悩み、なかなか仕事がうまくいかない悩みなど、ごく親しい人にしか相談できないようなことも相談できるので、安心感につながります。
安否確認をしてもらえる
担当者の家庭訪問により、安否確認もしてもらえます。近くに子どもが住んでいない、身寄りがないなど、一人暮らしで自身の健康に不安を抱えているときには嬉しい制度です。
医療費、介護費、教育費が免除になる
生活保護世帯になると、医療や介護の自己負担割合が0になります。つまり医療費や介護費がかかりません。また「教育扶助」として、義務教育就学中は学用品、給食費、学級費、課外クラブ活動費などの費用が支給されます。高校生になると「正業扶助」として学用品費や教材代が支給されます。
年金保険料が免除になる
生活保護の生活扶助を受けていると、年金保険料が免除になります。ただし免除期間については、将来年金として受け取れる額が少なくなってしまいます。その期間の年金額を満額にしたかったら、追納する必要があります。
生活保護を受けるときの注意点
メリットとデメリットを踏まえたうえで、生活保護を受ける際には以下の3つに注意しましょう。
「受給できる」「できない」は自己判断せず、まずは相談を
生活保護は「ぜいたく品を持っていると受給できない」「家や車があると申請が通らない」と思っている人がいるかもしれません。しかし、受給できるかどうかは資産の状況だけでなく、置かれている状況を見て判断されます。まずは相談するのが、安心への近道です。
例えば持ち家があったとしても、「売却してもまとまったお金にならず、家を手放すことでかえって困窮度が高まる」と判断された場合は、持ち家があることは不利に働きません。公共交通機関が発達していない地方では、車が唯一の移動手段であることが考慮され、所有が許されるケースがあります。
DVや虐待の加害者への親族照会はしないよう担当者に伝える
担当者が親族照会をしたとき、電話の相手先がもしDVや虐待の加害者であったら、自分の今の状況が相手に知られてしまいます。このような事情がある場合は、相手への照会をしないよう担当者に伝えましょう。
受給できる金額だけでなく、トータルで判断する
生活保護は「金銭的な保護」と「精神的な保護」を行ってくれます。受給できる金額だけで判断するのではなく、安否確認してもらえる、自立支援をしてもらえる、家計や仕事の悩みに乗ってもらえるといったトータルのメリットを考えて、申請するかどうかを判断しましょう。
まとめ
生活保護を受けている世帯はおよそ200万世帯に上り、保護率は1.62%となっています。生活保護世帯は、珍しい存在ではありません。困窮し、不安が強いようであれば、福祉事務所へ相談しましょう。
「もしかしたら受給できないかも」と思っても、相談すれば低利貸付の制度利用を勧められるなど、別の手段で安心感を得られるかもしれません。まずは自分が困っていることについて、生活保護のプロであるケースワーカーに打ち明けることが、自分の生活を建て直すために必要な一歩となります。