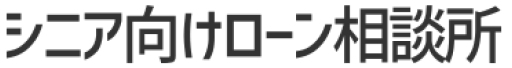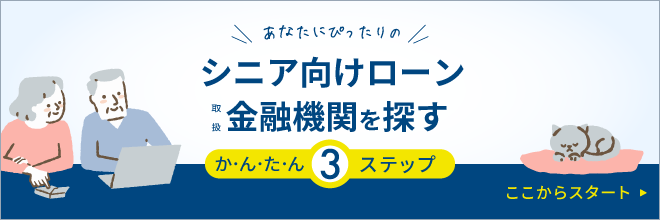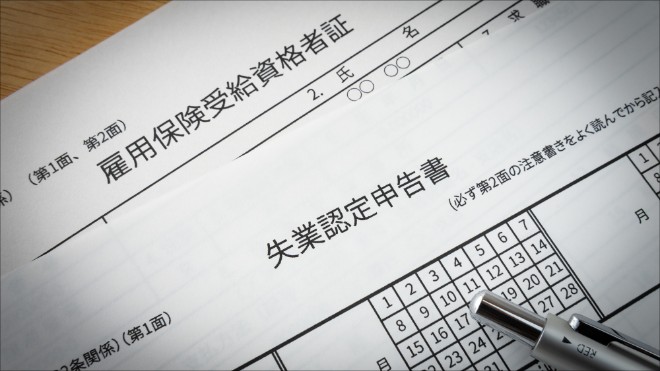60歳からの老後生活を見据えて、コンパクトな間取りの家を建てる、バリアフリーの住宅にリフォームする際、住宅ローンを組みたいと考える人も多いでしょう。
60歳から住宅ローンを組むには、老後の生活費を計算し借入金額の返済計画を考える必要があります。シニア層でも組めるフラット35やリバースモーゲージなどの商品も利用し、頭金を準備して毎月の返済額を抑えることや金利を確認して自分にあったプランを選ぶことが重要です。
60歳から住宅ローンは組めるのか?
住宅ローンの申し込み可能な年齢は20歳以上から70歳未満とする金融機関が多く、60歳からでも住宅ローンを組むことは可能です。
通常住宅ローンの返済期間は10〜35年に設定することが多いですが、完済時の年齢は80歳未満に設定されている金融機関がほとんどであるため、60歳から住宅ローンを組む場合は、返済期間は最長でも20年になります。
60歳以上でローンを組む場合は、現役層に比べて審査が厳しくなる傾向にある一方で、老後生活に向けて小さな間取りを希望されている場合や、住宅購入用の自己資金のある場合もあり組みやすい場合もあるでしょう。また、フラット35やリバースモーゲージなどシニアでも利用ができるローン商品もあります。
60歳から住宅ローンを組むときのリスクと注意点
借入期間が短くなるため、毎月の返済負担が重くなる
住宅ローンを組む年齢が高くなるほど、完済までの借入期間が短くなるため、毎月の返済金額が高くなります。
購入価格や建築費用を抑える、頭金を準備などして、理想的な返済負担率は年収の20%以下、多くても25〜30%までに抑えるようにしましょう。
老後資金が枯渇する
60歳以上でローンを組む場合、完済年齢が定年後になるため、退職後は退職金などの手持ち資金での返済や公的年金での返済をすることになり、老後資金を切り崩す必要が出てきます。
また、退職金や自宅を売却した資金を頭金として当てることで毎月の返済負担が減る一方で、手持ちの資金が少なくなるため、老後の資金に不安が残ります。
住宅ローンが払えなくなった場合、負債だけが残る
シニア層では、想定していたより退職金が少ない、退職後再雇用で就業しても給料が大幅に減ることで収入が減少する、病気やけがによる入院など予期せぬ出費の可能性があります。
住宅ローンが支払えなくなった場合、購入した住宅を売却して残債の支払いに当てることになります。
老後の生活費を計算して返済計画を立てる
シニア層で住宅ローンを組む場合は、老後の生活費を計算して返済計画を立てることが重要です。
総務省の家計調査報告によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の平均的な消費支出は23万6,696円(住居:15,578円を含む)とされています。その一方で、60歳以上の年金受給の月額平均は一人当たり厚生年金14万3,965円、国民年金は56,368円となっており、老後の資金計画を立てて住宅ローンを設定する必要があります。
総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2022年(令和4年)平均結果の概要」
厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 」
自分にあった金利や返済方法を選ぶ
住宅ローンの金利は申し込んだタイミングや融資が実行されたタイミングの金利で返済し続ける「全期間固定型」と、借入期間中に金利が変動する「変動型」があります。
変動型は、一般的に5年に一度金利の見直しが行われます。固定型に比べて金利が低く設定されていることが多い反面、将来的に金利が上昇すると月々の返済金額が増加し、なかなか元金が減らないということも考えられます。全期間固定型の場合は、市場で金利が下がってもその恩恵を受けることはできませんが、返済計画を立てやすいといメリットもあります。
複数の借入先で金利や返済方法を比較して自分にあったプランを選ぶようにしましょう。
団体信用生命保険への加入が必要になる
住宅ローンを組む際、団体信用生命保険(以下、団信)への加入が義務となることがあります。団信とは、住宅ローン返済中に契約者が死亡や高度障害などにより支払いができなくなった場合に、生命保険会社が住宅ローンの残債分を保険金として銀行に支払う仕組みです。団信の保険料は住宅ローンの金利に上乗せされることが多いため、毎月の支払額が増えます。
また、現在の健康状態や、病歴によっては団信に加入できない場合もあり、その場合は一部の持病があっても加入できる「ワイド団信(引受条件緩和型団信)」や、団信への加入が任意である「フラット35」を検討しましょう。
60歳からの住宅ローンで審査を通すポイント
頭金を準備する
同じ物件を購入するとしても、頭金を準備して借入の希望金額を抑えることで返済額が低くなり、審査が通りやすくなります。頭金がないと返済総額が高くなり金利も増えるため、ローンを組めなくなる場合もあり注意が必要です。購入住宅の20〜25%を準備しておくのが一般的とされており、60歳以上で住宅ローンを組む場合はそれ以上に準備しておくのが理想的です。退職金などまとまったお金が入ってきた場合には繰り上げ返済も検討しましょう。
不動産評価の高い家を購入する
金融機関としては、契約者が万が一住宅ローンを返済できなかった場合や死亡時に、負債分を担保となる自宅を売却して当てるため、担保となる住宅の価値が重要な指標となります。
建物は築年数の経過とともに資産価値は下がるため、周辺環境が充実している地域や交通状況の利便性の良い場所、災害リスクの少ない土地など需要の高い土地を選ぶのも一つの手段です。
親子リレーローンを利用する
二世帯住宅を建てる場合や子どもが同居している場合などは、親子リレーローンを利用する方法もあります。
一つの物件に対して、親と子とそれぞれがローンを契約することで返済期間が長くなり、審査も通りやすくなります。安定した収入があることや、借入時に子どもの年齢が18歳以上70歳未満、完済時の子どもの年齢が80歳未満などの条件があります。
60代から住宅ローンを組む時に使える補助金制度と減税制度
住宅ローンを組む際に使用できる補助金制度や減税制度についてご説明します。
ZEH支援事業や地域型住宅グリーン化事業などは併用することができないため、ご自身の住宅に合わせた制度を選ぶ必要があります。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
国土交通省が推進する「長期優良住宅化推進事業」は既存住宅を長く住める家にリフォームすることへの支援した制度です。住宅診断を行った上で、工事後に耐震性や劣化対策、省エネルギー性が確保されていることを条件にリフォーム工事等に要する費用が補助されます。
リフォーム工事など補助対象となる費用の1/3で、限度額は100万円/戸です。
国土交通省「令和5年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の募集を開始します!」
ZEH支援事業
高断熱、省エネルギー、電力創出によって、生活で消費するエネルギーの収支がゼロになることを目指した住宅をZEH(ネット・ゼロ・エネルギ・ハウス)といいます。
ZEHを戸建で建てる場合、55万円/戸の補助があります。強化外皮基準(屋根、壁、床などの断熱性能を判断する基準)や、ZEHビルダーや、ZEHプランナーが設計・建築する住宅であるなどの条件を満たす必要があります。
次世代ZEH+実証事業
ZEHの条件を満たしつつ、さらにエネルギー消費量の25%以上削減、蓄電システムの導入などの条件を満たすことで「ZEH+」や「次世代ZEH+実証事業」に申請することができ、100万円/戸の補助を受けることができます。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ「2023年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」
LCCM住宅整備推進事業
ZEHの条件に加えて、住宅の建設時、運用時、廃棄時において二酸化炭素炭素排出量を削減に取り組んだ住宅のことをLCCM住宅と呼び、
一定の基準を満たすことで、設計費や建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用の1/2が補助され、補助限度額は140万/戸です。
LCCM住宅整備推進事業実施支援室「LCCM住宅設備推進事業 概要」
地域型住宅グリーン化事業
省エネルギーで耐久性のある木造住宅を新築する場合、条件を満たせば国土交通省が主催する「地域型住宅グリーン化事業」に申請することができます。
地域型住宅グリーン化事業に参画している中小工務店が申請をおよび受け取りを行い、最大110万円の補助金を受けることができます。(こどもエコ活用タイプを除く)
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、住宅ローンを組み物件を新築・購入した場合、年末の住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除する制度です。所得税から控除できない金額がある場合は、一部住民税からも控除され、最大13年間適用されます。
財務省ホームページ「「住宅ローン減税」について教えてください。」
固定資産税の減税
令和6年3月31日までに新築された住宅の場合、床面積など一定の条件を満たした住宅であれば固定資産税の減税対象になります。戸建ての場合、「住居部分の床面積が2分の1以上」かつ「床面積が50㎡以上280㎡以下」であれば3年間、新築マンションの場合「居住部分が専有部分の2分の1以上」かつ「床面積が50㎡以上280㎡以下」であれば5年間、固定資産税が1/2になります。
バリアフリー改修に関する特別処置
バリアフリーのために改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。適応期限は令和5年12月31日までですが、バリアフリーに優れた住宅を次世代に残す目的での処置であるため、今後同様の処置がある可能性もあります。
60歳の住宅ローンを検討するならリバースモーゲージ
リバースモーゲージの概要
シニア世代におすすめの住宅ローンが「リバースモーゲージ」です。
リバースモーゲージとは、お住まいの自宅を担保として金融機関から融資を受けるローンです。銀行などの金融機関だけでなく、自治体が福祉サービスの一環として取り扱っている場合もあります。一般的な住宅ローンは、契約時に自宅を購入するためのまとまった資金を借り、毎月返金していく仕組みですが、リバースモーゲージは自宅の評価額に応じて融資を受け、契約期間中は利息分のみを毎月返済し、契約終了時や死亡時に、自己資金や自宅を売却して元金を返済します。
リバースモーゲージの仕組み
リバースモーゲージは、自宅の評価額の30~60%程度を上限として融資を受けることができ利息分を返済しながら、担保としている自宅に住み続けることができる住宅ローンです。
基本的には契約者の死亡時に銀行が自宅を売却して借入金の返済にあてるため、自宅を相続することはできない場合があります。そのため、契約時には相続人の同意が必要となります。また、担保物件である自宅を売却した際に、借入金額を下回った場合は、相続人が債務を支払うリコース型と、相続人に請求がいかないノンリコース型があります。
リバースモーゲージの特徴
基本的にリバースモーゲージの対象となるのは戸建てで、契約者と配偶者以外は同居できないなどの条件がつくことがあります。
融資の使用用途は、自宅の購入やリフォームだけでなく生活資金や介護費用、レジャーなどの娯楽費用にも当てることができるため、老後資金を確保してゆとりのある老後生活を過ごしたい方におすすめです。
まとめ
60歳以上でもリバースモーゲージなどシニア向けのプランを選べば、住宅ローンを組める可能性は高くなります。老後の生活を圧迫しないように、借入金額や頭金、金利の変動や諸経費を考慮して毎月の返済額を決めましょう。
プランや借入先を検討して無理のない返済計画を立てることがより快適な老後生活をおくる秘訣です。