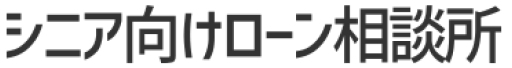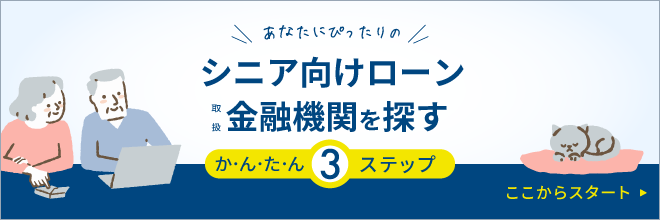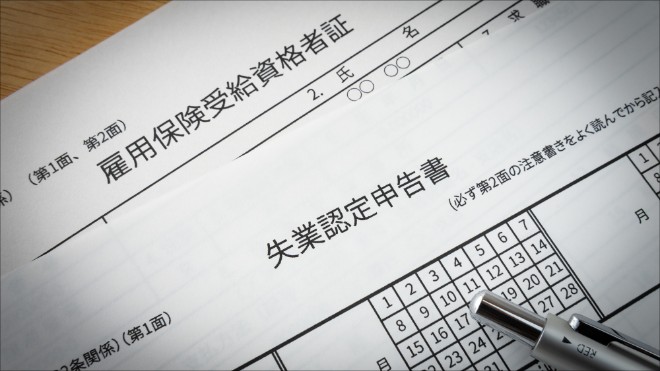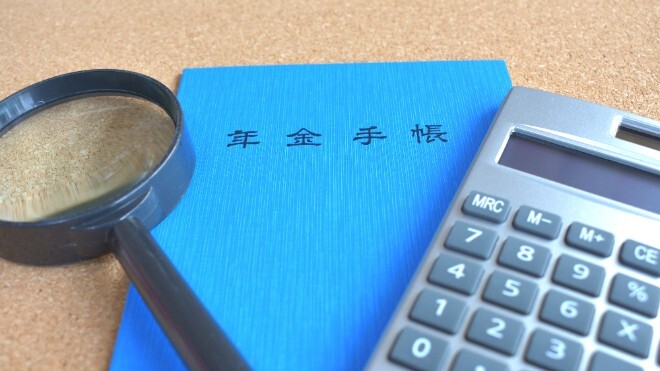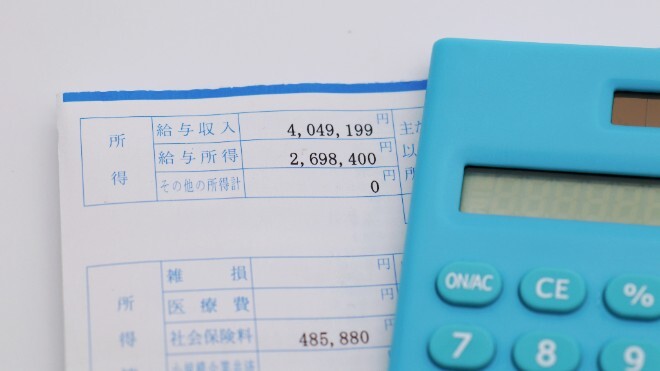共同名義、共有名義の不動産を持っているなら、共同所有を解消して一人の名義にしておくのがおすすめです。共同名義の不動産は、相続が生じてもそのままにしておくと後で実際の共有者が誰かが分からなくなる可能性があるためです。ただ、不動産を購入するときは単独名義よりも個人負担が少ない、夫婦で共同名義にすれば住宅ローン控除がお互いに使えるなどのメリットもあります。共同名義のメリットやデメリット、売却時の注意点を解説します。
不動産の共同名義とは?
不動産の共同名義とは、複数の人が一つの不動産を共同で所有している状態をいいます。登記事項証明書(権利書)には複数人の名前が共同名義人として並び、それぞれ持分が記されます。持分とは、全不動産のうち、その人が所有している割合のことです。
不動産が共同名義になるのは、遺産を平等に相続したい場合や、夫婦で不動産を購入する場合です。また、不動産を手に入れたくても個人の資金では足りないとき、共同名義とする形で親族などに援助してもらう場合も考えられます。
不動産の共同名義のメリットとデメリット
不動産の共同名義のメリットとデメリットは、それぞれ以下のようなものです。
メリット①高額な住宅ローンを組める
共同名義で不動産を購入すれば、一人では購入することのできない高額な不動産にも手が届きます。名義人それぞれに対して審査が行われ、収入を合算した形で借入可能額が決まるためです。
メリット②土地があってお金がない相続の問題を解消できる
遺産相続の際、持ち家はあるのに現金としての資産が少なく、相続人全員に遺産を平等に分けられないというのはよくある話です。ときには揉めに揉め、子世代の思い出が詰まった実家を売却することになってしまうケースもあります。
遺産として承継した持ち家を複数の相続人で共同名義にすれば、平等な相続としてみんなが納得しやすくなります。
メリット③共有者みんなが住宅ローン控除を受けられる
不動産の名義人として名を連ねていれば、住宅ローン控除を受けられる可能性があります。住宅ローン控除とは、「完済までの期間が10年以上ある」「控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である」などの要件を満たせば、住宅ローンの年末残高に一定割合を乗じて求めた金額を控除額の上限として所得税などから控除できる制度です。
夫婦の共同名義で不動産を購入した場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を使えることになるため、単独名義よりも家計としての節税効果がアップします。
デメリット①自由な売却や貸出ができない
共同名義人全員の同意がなければ、不動産を売却することができません。また、貸出やリフォームについては、共同名義人の過半数からの合意が必要になります。3人で共有しているのであれば、賛成派が2人以上という状況にならなければ家の修繕もできないということです。
デメリット②夫婦2人の共同名義は離婚時に問題となる
これは共同名義に限った話ではありませんが、もし夫婦が離婚してしまった場合には、どちらがその家へ住み続けるかが議論されることになります。しかし、もともと共同名義だからと高い住宅ローンを組んでいると、家に残った方が単独で高額な住宅ローンを返済していかなければなりません。
とても支払いきれる金額ではないと悩んだ結果、家を売却するという結論になってしまうことも多いでしょう。
デメリット③子世代に迷惑がかかる可能性がある
共同名義では、名義人全員の合意がなければ不動産売却ができません。もしも前の世代で相続を円滑に進めるため共同名義を選んだとしたら、次の相続が発生したとき、相続人は共同名義人になっている親族一人ひとりに事情を説明し、売却の合意をとる必要があります。
また、共同名義人だった親族がすでに他界していたら、その相続人に了解をとらなければなりません。こうして子世代は、空き家となった実家を、ほとんど他人ともいえる人とコミュニケーションを取って売却する羽目に陥るかもしれないのです。共同名義は、早めに解消しておいた方がいいといえるでしょう。
不動産の共同名義の解消方法
デメリットの項で示したように、とくに相続がややこしくならないようにするためには、共同名義を早めに解消しておくべきです。自宅の相続のため、生前に行える共同名義の解消方法は、以下の3つです。
他の人の共有部分を買い取り単独名義にする
共有名義を解消したうえで自宅に住み続けたい場合、最もシンプルなのがこの方法です。他の人の共有部分を、それぞれの持分に従った金額を支払って買い取ります。買取金額は他の名義人との交渉で決めますが、市場価格に持分を乗じた金額にすると、納得度が高いでしょう。
問題は、他の名義人の持分を買い取れるだけの資金があるかどうかです。また、他の名義人の合意が取れるかどうかもポイントになります。他の名義人が2人以上いた場合、誰が1人に拒否されてしまったら、お金を用意したところでこの方法はとれません。
一つの土地を複数に切り分け、それぞれを単独名義にする
他の名義人の持分を買い取れるだけの資金がない場合は、分筆を視野に入れましょう。分筆とは、登記簿で一筆の(一つの)土地とされているものを、複数に分割することです。名義人の持分に応じて複数に分筆し、それぞれの土地を、それぞれの名義人の単独名義とします。
ただ、この方法は、所有する土地と建物の位置関係によっては現実的ではありません。土地いっぱいに自宅が建っている場合は切り分けが不可能ですし、庭や家の裏手に土地がある場合も、持分通りにきちんと切り分けられるとは限らないためです。
また、土地が小さくなると売却しづらくなります。とくに一軒家を建てられるかどうか迷うような小さな土地は、まず売れないでしょう。その場合、持分通りであっても共同名義人の許可が得られる可能性は低くなります。
自宅まわりに広い庭や土地があり、その一帯が一つの土地として共同名義になっているような場合は、分筆を検討してみましょう。
自分亡き後、空き家を売却するよう相続人と共同名義人に頼んでおく
共有不動産を売却し、売却益を持分通りに共同名義人へ振り分ければ、共同名義としてはかなり納得度の高いものとなります。ただ、現在自分が住んでいる自宅を手放すのは現実的ではないでしょう。
「自分亡き後、空き家となった家を売却してほしい」と、共同名義人や相続人に頼んでおくのはいかがでしょうか。スムーズに売却が進むよう、相続人には共同名義人全ての連絡先を渡しておきます。共同名義人に話をするとき、相続人に同席させると理想的です。
共同名義の不動産を売却するときの注意点
共同名義の不動産を売却することを決めたなら、以下の3点に注意しましょう。
売却価格を勝手に決めない
不動産を売却するときは、共有名義人のうち誰か一人が代表になり、不動産会社とのやりとりを行うことになるでしょう。売却価格を設定するときは、自分一人で決めずに他の名義人の意見を必ず参考にしましょう。売却が決まった後で「安く売りすぎでは」などと言われ、トラブルに発展することがあります。
税金や手数料の費用負担について伝えておく
不動産を売却すると、取得費や譲渡にかかった費用を抜いた金額が譲渡所得とみなされ、所得税と住民税がかかります。税金がかかることをしっかり伝えておかないと、トラブルになってしまう可能性があります。
また、譲渡するときに不動産会社へ手数料を支払ったり、リフォームをするなどの条件付きで譲渡となったりする場合があります。譲渡にかかった費用は全て売却金から差し引いたうえで持分通りに分けることを、あらかじめ了承してもらいましょう。
共同名義のデメリットを伝え円満解決を目指す
いざ売却となると、「両親から相続した家を売るのは辛い」などの理由で売却を拒む名義人が出るかもしれません。名義人の気持ちは尊重すべきですが、売却しないと後の子世代が困ってしまうなどのデメリットをしっかり伝えるのが大事です。円満に売却できるようコミュニケーションを取りましょう。
まとめ
以上、不動産の共同名義について解説しました。共同名義になっているかどうかは、権利書を確認しないと分からない場合もあります。もしも共同名義になっていたら、後の世代のためにも生前にきちんと解消しておくのがおすすめです。また、次に相続が発生した場合も、共同名義にするという解決方法をとることのないよう注意しましょう。