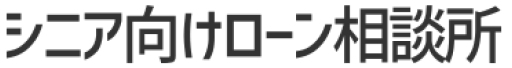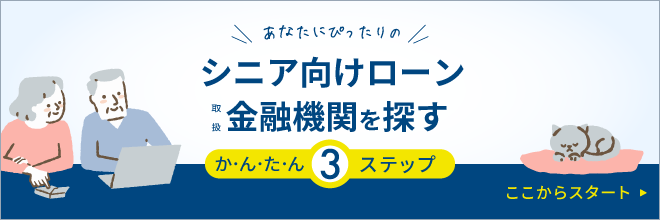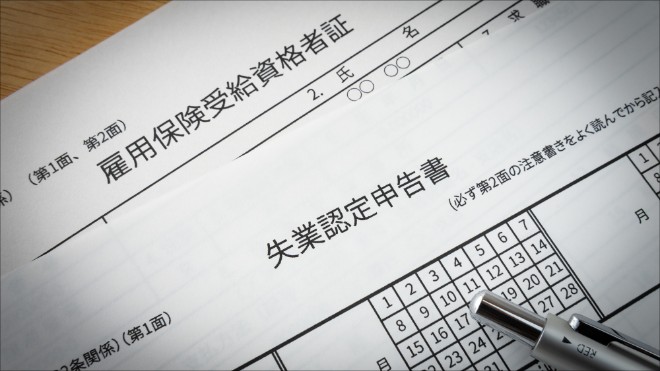退職金制度の仕組みは企業によって違いますが、勤続年数が20年を超えると退職所得控除額がアップするようになっています。つまり退職金のうち、税金がかかる金額が減ります。また、退職金は一時金でもらえば退職所得として控除が適用されますが、年金でもらうと特別な優遇がありません。退職金の基礎知識や退職金の相場、計算方法などについて解説します。最後には、退職金以外の老後資金の貯え方についてもご案内します。
退職金の基礎知識
まずは退職金の基礎知識として、仕組みや支給方法、かかる税金について解説します。
退職金の仕組み
退職金の仕組みは企業によって違いますが、おおむね以下の2つのパターンに分けられます。
- 定額制
勤続期間別に退職金額が設定されているパターンです。勤続期間が長いほど、受け取る金額が大きくなります。
- 給与比例制
全期間の平均給与、あるいは退職時の最終給与を基準として、所定の率をかけて支給されるパターンです。定額制とは違い、受け取る人によって退職金の金額が変わります。
退職金の支給方法
退職金の支給方法は、以下の3つです。3つのうちいずれかを選べる企業もあれば、1つの受け取り方法しか採用していない企業もあります。
- 退職一時金
退職時に退職金を一括して受け取る方法です。起業する、リフォームするなど、退職を機にまとまった出費を計画している人に向いています。
- 退職年金
退職金を分割して、毎年いくらかずつ受け取る方法です。老後の家計が不安で、安定した生活を送りたいと考えている人に向いています。
- 退職一時金と退職年金の併用
いくらかまとまった金額を一括して受取り、残りの金額は分割していくらかずつ受け取る方法です。この併用ができる企業では、後に解説するような税金対策のために併用を選ぶ人もいます。
退職金にかかる税金
一時金として受け取る場合と、年金として受け取る場合とでは、所得の種類が違い、かかる税金が違います。
退職一時金は「退職所得」とみなされ、特別な控除があります。退職金は大きな収入になることが多く、所得税の税率をそのまま適用してしまうとかなりの金額を税金として納めなければならなくなります。定年後の生活を支える意味を持つ退職金に多額の税金をかけるのはふさわしくないため、優遇されているのです。
一方、退職年金は「雑所得」とみなされ、他の公的年金等と合計して計算された金額から公的年金等控除額を差し引いた金額に税金がかかります。公的年金控除額は、受給者の年齢や収入金額によって変わります。
退職金にかかる税金の詳しい計算方法は、後の章でもご紹介します。
退職金の相場
退職金としていくらもらえるのか、気になってしまう人も多いでしょう。会社規模別、業種別、勤続年数別に退職金の相場をまとめました。参考にしてください。
会社規模別
大企業の退職金については、中央労働委員会が資本金5億円以上かつ労働者1,000人以上である企業を対象に行っている「賃金事情等総合調査」で確認することができます。
令和5年の賃金事情等総合調査によると、定年退職時のモデル退職金額(新卒入社し普通程度の能力技術で勤務した場合の退職金)は、大学卒で2,858万4,000円です。高校卒で2,162万5,000円です。
中小企業の退職金については、東京都産業労働局が隔年で従業員10人~299人の中小企業の退職金事情を調査しており、都内企業を対象とした調査ではありますが、概要をつかむことができます。令和4年版「中小企業の賃金・退職金事情」によると、定年時のモデル退職金支給額は、大学卒が1,091万8,000円、高専・短大卒が983万2,000円、高校卒が994万円でした。
業種別
業種別の退職金相場については、こちらも東京都産業労働局が発行している令和4年版「中小企業の賃金・退職金事情」で調査されています。あくまで東京の中小企業における退職金事情になりますが、以下を参考にしてください。
【業種別 定年退職した場合のモデル退職金】※-:データなし
|
業種 |
高校卒 |
高専・短大卒 |
配偶者+子ども3人 |
|
建設 |
1,177万円 |
1,233万3,000円 |
1,313万8,000円 |
|
建設 |
1,080万4,000円 |
1,066万8,000円 |
1,148万7,000円 |
|
情報通信 |
864万9,000円 |
876万6,000円 |
1,154万5,000円 |
|
運輸、郵便 |
821万9,000円 |
665万9,000円 |
893万2,000円 |
|
卸売、小売 |
1,019万4,000円 |
984万3,000円 |
1,088万4,000円 |
|
金融、保険 |
- |
1,557万4,000円 |
1,725万5,000円 |
|
不動産、物品賃貸 |
- |
- |
1,725万5,000円 |
|
学術研究、専門・技術サービス |
- |
895万6,000円 |
1,007万1,000円 |
|
生活関連サービス、娯楽 |
1,129万6,000円 |
1,020万1,000円 |
1,104万2,000円 |
|
教育、学習支援 |
- |
- |
656万9,000円 |
勤続年数別
勤続年数別の調査も参考に掲載します。
- 大企業の場合
令和5年版「賃金事情等総合調査」によると、大企業の「大学卒・事務・技術労働者、総合職相当、自己都合」における勤続年数別のモデル退職金は以下の通りです。
|
勤続年数 |
退職金総額 |
|
勤続3年(25歳) |
34万1,000円 |
|
勤続5年(27歳) |
63万1,000円 |
|
勤続10年(32歳) |
182万8,000円 |
|
勤続15年(37歳) |
402万7,000円 |
|
勤続15年(37歳) |
761万9,000円 |
|
勤続25年(47歳) |
1,186万3,000円 |
|
勤続30年(52歳) |
1,771万8,000円 |
|
勤続35年(57歳) |
2,303万9,000円 |
|
勤続38年(60歳) |
2,380万8,000円 |
- 中小企業の場合
令和4年版「中小企業の賃金・退職金事情」によると、東京都の中小企業における勤続年数別のモデル退職金(自己都合退職の場合)は以下の通りです。
|
勤続年数 |
モデル退職金(高卒) |
モデル退職金(高専・短大卒) |
モデル退職金(大卒) |
|
10年 |
90万7,000円 |
98万7,000円 |
112万1,000円 |
|
15年 |
170万5,000円 |
183万7,000円 |
212万1,000円 |
|
20年 |
272万9,000円 |
292万4,000円 |
343万1,000円 |
|
25年 |
397万1,000円 |
423万円 |
490万6,000円 |
|
30年 |
532万5,000円 |
565万8,000円 |
653万6,000円 |
退職金の計算方法
ここで、受け取る退職金のうちいくらが税金として引かれるのかを解説します。先にお伝えしたように、退職金を一時金として受け取る場合と、年金として受け取る場合では、計算方法が違います。
一時金として受け取る場合
退職一時金は「退職所得」とみなされ、退職所得控除額が適用されます。退職所得控除額は、勤続年数によって異なり、勤続年数が20年を超えると優遇されます。控除額を引いた金額に、税金がかかります。退職所得控除額の計算方法は以下の通りです。
|
勤続年数 |
退職所得控除額 |
|
20年以下 |
40万円×勤続年数 |
|
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を引き、さらに1/2を掛けた金額となります。
年金形式で受け取る場合
退職金を年金形式で受け取る場合は、他の年金収入と合わせて雑所得とし、公的年金等控除額を計算します。控除額は、公的年金等にかかる雑所得以外の合計金額が1,000万円以下の場合、以下の通りです。
公的年金等に係る雑所得以外の合計金額が1,000万円以下
|
公的年金等に係る雑所得以外の合計金額が1,000万円以下 |
||
|
年金を受け取る人の年齢 |
(a)公的年金等の収入金額の合計額 |
(b)公的年金等に係る雑所得の金額 |
|
65歳未満 |
60万円以下 |
0円 |
|
60万円超130万円未満 |
収入金額の合計額-60万円 |
|
|
130万円以上410万円未満 |
収入金額の合計額×0.75ー27万5,000円 |
|
|
410万円以上770万円未満 |
収入金額の合計額×0.85ー68万5,000円 |
|
|
770万円以上1,000万円未満 |
収入金額の合計額×0.95ー145万5,000円 |
|
|
1,000万円以上 |
収入金額の合計額-195万5,000円 |
|
|
65歳未満 |
110万円以下 |
0円 |
|
110万円超330万円未満 |
収入金額の合計額-110万円 |
|
|
330万円以上410万円未満 |
収入金額の合計額×0.75ー27万5,000円 |
|
|
410万円以上770万円未満 |
収入金額の合計額×0.85ー68万5,000円 |
|
|
770万円以上1,000万円未満 |
収入金額の合計額×0.95ー145万5,000円 |
|
|
1,000万円以上 |
収入金額の合計額-195万5,000円 |
|
公的年金等にかかる雑所得以外の合計金額が1,000万円を超える場合や、平成17年から令和元年分までの所得について知りたい場合は、以下をご確認ください。
退職金以外の老後資金の貯え方
「退職金をアテにしていたけれど、十分な老後資金を得られるとはいえない」と感じたなら、老後資金を貯えましょう。今からでも、決して遅くはありません。以下のような方法があります。
NISA
NISAは個人で少額投資をする人のための制度です。通常、投資を行うと分配金や譲渡益に20%の税金がかかりますが、NISAの制度枠内では非課税となるため、優遇措置に惹かれて始める人も多いでしょう。
また、投資対象商品は比較的リスクの少ない物に絞られているため、初心者でも安心して始められます。2024年から大きく制度を変え、非課税枠や期間が大きく緩和されました。本格的に老後資金を貯めたいと感じている方にもおすすめです。
iDeCo
iDeCoは「個人型確定拠出年金」の愛称です。毎月掛け金を拠出して運用を行い、60歳以降に掛金と運用益の合計額をもとに給付を受けます。iDeCoの運用益は非課税で、掛金は全額が所得控除の対象となります。税金対策としても優れた老後資金対策です。
なお、老後に年金を受け取るときは、一時金形式と年金形式、どちらかを選ぶことができます。
個人年金保険
個人年金保険とは、月々の積立金や受け取る時期を決め、一定の年齢に達したら積立金をもとに年金を受け取れる保険です。投資商品であるiDecoとは違って保険商品なので、自分で投資運用を行う必要はありません。決まった金額を確実に受け取りたい人におすすめです。
公的年金にプラスして、毎月いくらかほしい人にはおすすめの方法です。被保険者が生存している間はずっと年金を受け取れる終身保険、生存中に一定期間の間だけ受け取れる有期年金、生存しているか否かにかかわらず一定期間は本人か家族が年金を受け取れる確定年金があります。
定期預金
定期預金は預かり入れ期間を決めて利用する預金で、普通預金に比べると金利が高くなっています。預かり入れ期間を長くして定年後に受け取れるようにすれば、手軽にお金を増やせます。今普通口座がある金融機関で始められるため、手続きが簡単で便利です。毎月一定額を積み立てる「積立定期」もあります。
投資信託
少額から投資を行いたい、自分で運用するのは不安という方には、投資信託がおすすめです。投資の専門家があなたのかわりに運用してくれ、またたくさんの投資家から預かったお金をまとめて分散投資するため、個人では買いにくい海外の株式や債券にも投資が可能になります。
ただし投資信託は長期運用すればするほど安定した利益が出るのが特徴です。長くお金を預ける余裕がない方には向いていないため、注意しましょう。
まとめ
ご紹介したように、退職金制度は勤続年数が長ければ長いほど優遇される仕組みになっています。新卒で企業に入社し、ずっと一箇所で勤務し続けてきた人にとっては何よりのご褒美となるでしょう。
ただ、どんなに勤続年数が長い人であっても、退職金があれば老後は安心かというと、そうとは言い切れません。退職が近い人は配偶者などとも相談し、定年後の家計をシミュレーションしてみましょう。ねんきんネットを使って受け取れる公的年金を試算し、年金で家計を賄えるかどうか、突発的な出費に対応できる資金はあるかを確認しておくのが大事です。