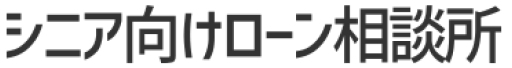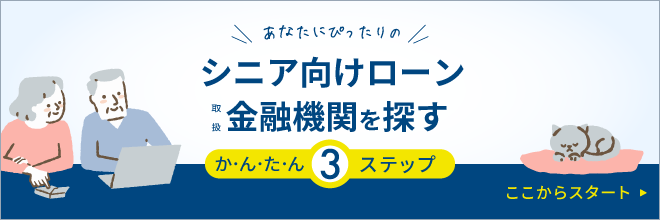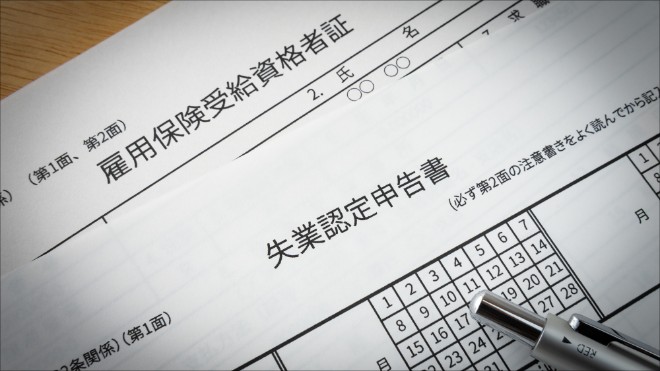遺産相続の際、子供にどのくらいの相続税がかかるのかは、被相続人となる親にとっても、相続人となる子供にとっても知っておきたいものです。そもそもの基礎控除額は相続人の数だけで計算しますが、法定相続人が配偶者と子供である場合と、子供だけが相続する場合とでは、相続税額が違ってきます。子どもにかかる相続税の計算方法と、利用できる控除制度について解説します。
相続税の計算方法
相続税とは、遺産の総額に応じて税務署に収める税金です。相続税には基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税がかかることはありません。したがって、相続税がいくらになるのか計算するときは、まず基礎控除額がいくらになるのかを知り、遺産総額がその額を超えるかどうかを確認することから始めます。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」です。つまり、法定相続人が1人の場合、遺産総額3600万円までは、相続税がかかりません。2人の場合は、4200万円までかかりません。
法定相続人とは、法で定められた相続人を指します。法定相続人は、以下のように順位が定められています。
【被相続人から見て】
- 配偶者は必ず法定相続人になる
第一順位:直系卑属(子供。子どもがすでに死亡している場合は孫、それもいなければひ孫)
第二順位:直系尊属(父母。父母がすでに死亡している場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥姪)
第一順位の人が存在する場合は、第二順位以下の人は、法定相続人になりません。第一順位がいない場合のみ、第二順位の人が法定相続人となります。第一、第二順位の人がいない場合のみ、第三順位の人が法定相続人になります。
例えば、Aさんが亡くなり、配偶者Bさんと2人の子供が残されたなら、Bさんと子供2人、合計3人が法定相続人となります。そのほかの人は、法定相続人にはなりません。この場合の基礎控除額は、「3000万円+3人×600万円」で、4800万円です。
子供にかかる相続税
遺産相続が基礎控除額を超え、どうやら相続税がかかりそうということになったら、それぞれの法定相続人に、法にのっとった相続分割の割合で遺産が分配されたと仮定して、各相続人の税額を計算します。ここでは、相続人が子供のみの場合と、配偶者と子供の場合に分けて解説します。
相続人が子供のみの場合
仮に子供が2人の場合、法定相続分は、2人の子にそれぞれ2分の1ずつとなります。課税となる遺産の総額が2000万円であれば、それぞれ1000万円ずつが分配されます。ここで、相続税の早算表を使って税率を割り出し、税額を算出します。
【相続税の速算表】
|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1000万円以下 |
10% |
– |
|
3000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
5000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
|
3億円以下 |
45% |
2700万円 |
|
6億円以下 |
50% |
4200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7200万円 |
【課税遺産額】2000万円
【法定相続人】子供2人
【それぞれの子どもの相続税額】1000万円×10%=100万円ずつ
【相続税の総額】100万円×2人=200万円
となります。
相続人が配偶者と子供の場合
仮に相続人が配偶者と子供1人の場合、法定相続分は、配偶者1/2、子供1/2となります。課税となる遺産総額が2000万円であれば、一人1000万円ずつ分配されることとなります。
ここでも先の速算表を使えば、
【課税遺産額】2000万円
【法定相続人】配偶者、子供1人
【それぞれの相続税額】1000万円×10%=100万円ずつ
【相続税の総額】100万円×2人=200万円
となりそうですが、これは配偶者控除を活用しない場合の税額です。
配偶者控除とは、配偶者が遺産相続をする場合の制度です。次の金額のどちらか、多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、実際の相続税額は、以下の通りになります。
【課税遺産額】2000万円
【法定相続人】配偶者、子供1人
【それぞれの相続税額】1000万円×10%=100万円ずつだが、配偶者は、配偶者控除の適用になり0円
【相続税の総額】100万円×1人=100万円
以上のように、配偶者がいるかいないかで、相続税額はかなり変わってきます。
子供が相続するときに利用できる控除制度
配偶者控除のように、子供にも、相続のときに利用できる控除制度があります。主に、以下の3つです。
小規模宅地等の特例
居住用、事業用の小規模宅地を相続する場合、一定の要件を満たせば、その不動産の相続税評価額を最大80%まで減額できます。また、自分で事業を営んでおらず一定の法人に貸し付けていた宅地の場合も、減額できる可能性があります。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(国税庁)
未成年者控除
子供が20歳未満であれば未成年控除が受けられます。子供が満20歳になるまでの年数、1年につき10万円が、相続税額から差し引かれます。子どもが15歳であれば、満20歳になるまでに5年あるため、50万円が差し引かれます。
障害者控除
子供が障害者であり、85歳未満であるときは、相続税の額から一定金額が差し引かれます。満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)が差し引かれ、差し引き金額の方が相続税額よりも大きい場合は、差額分がその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引かれます。
参考:No.4167 障害者の税額控除
その他、相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、支払い済みの贈与税額を差し引き出来る「暦年課税分の贈与税額控除」や、今回の相続の10年以内に以前の相続があった場合に一定の金額が差し引かれる「相次相続控除」があります。
子供が相続するときの注意点
以上を踏まえたうえで、子供が遺産を相続するときの注意点を3つご案内します。
「お父さんのとき」と「お母さんのとき」では、トータルの相続税が違う
例えば、以前父親を亡くしたときに相続を経験しているからといって、母親のときも同じような相続になるとは限りません。相続人が減っているため基礎控除額が減り、また配偶者控除が使えないぶん、相続税の負担は重くなる傾向にあります。「前回も今回も、同じようなもの」と捉えず、きちんと計算するようにしましょう。
親の家の価額を評価したら、小規模宅地等の特例に当てはまらないか検討する
遺産の総額をみて「これは相続税がかかってしまうに違いない」と感じたら、まずは小規模宅地等の特例に当てはまらないかを検討しましょう。不動産の相続税評価額が減額されると、ぐっと遺産総額が減る場合が多いものです。
子供が未成年者や障害者の場合は特例に注意
子供が未成年者、障害者の場合には、必ず特例を参照し、控除額を確認しましょう。相続人本人は、特例があると気づくことが困難です。同じく相続人となっている兄弟姉妹や後見人、扶養義務者が気づいてあげましょう。
まとめ
以上のように、被相続人の配偶者がすでに亡くなっており、子供だけが相続人となる場合には、相続税がかかる可能性が高くなります。預貯金が少なくても、例えば都心の一等地に家があるなら、相続税は他人事ではありません。なるべく早めに想定される相続税を計算し、対策するのがおすすめです。