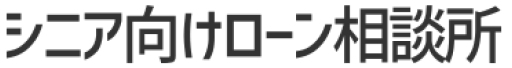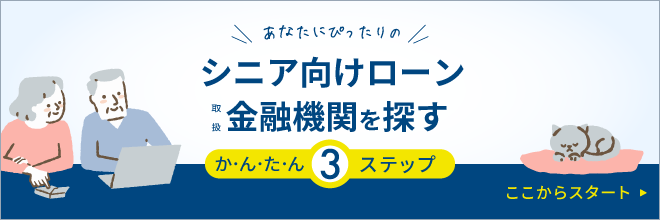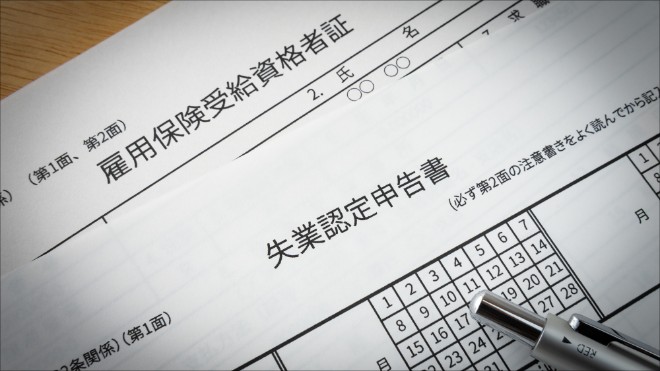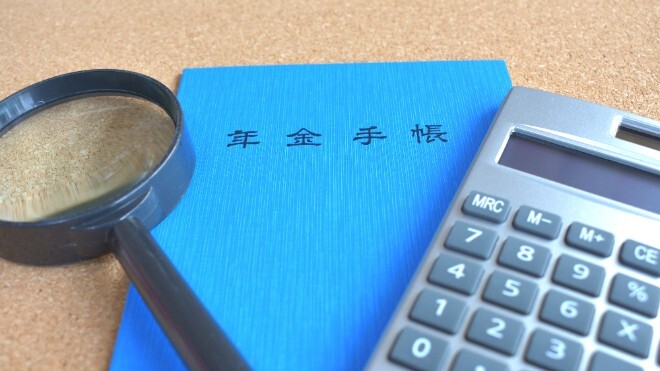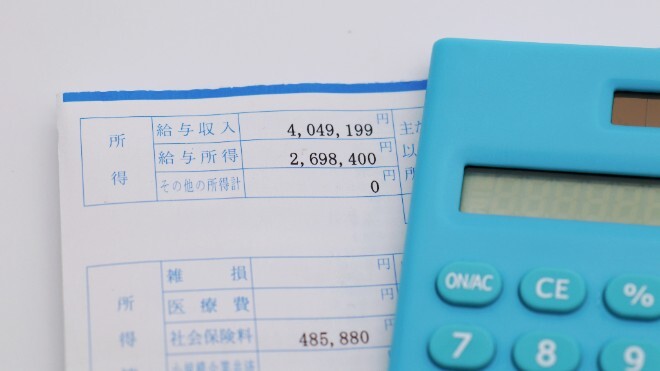ポンジ・スキームという言葉をご存じでしょうか。投資詐欺の手口の1つで、投資詐欺の9割以上がこのポンジ・スキームであるといわれています。「元本保証」「無リスク」「高利回り」といった条件の良すぎる投資話は疑ってかからなければなりません。昨今、投資の重要性が注目されていることもあり、これから投資を始めたいと考えている人もいるでしょう。投資詐欺に遭わないためのポイントを解説します。
ポンジ・スキームとは
ポンジ・スキームとは、アメリカの詐欺師「チャールズ・ポンジ」から取られた名称で、投資詐欺の手法を表します。まずはポンジ・スキームの概要や過去の事件、投資詐欺の被害状況について解説します。
ポンジ・スキームの概要
ポンジ・スキームでは、まず「元本保証」「高配当」「高利回り」といった好条件の投資案件で、出資者から資金を集めます。そして実際には運用せず、本人や他の投資家から預かった資金をそのまま配当金として還元します。
しかし、それではだんだん資金が枯渇していくため、どんどん新規の顧客を募り、すでにいる投資家へ還元するという手法を繰り返します。当然ながら、新規顧客が思うように獲得できなければ資金は枯渇していきます。
この詐欺的な配当システムが破綻してきたタイミングで、詐欺師は投資家から預かった巨額の資金を持ち去り、音信不通になってしまいます。顧客は大金を持ち去られたまま、詐欺師が見つからなければ泣き寝入りすることになってしまいます。
過去の事件
ポンジ・スキームが世間を賑わした有名な事件として、1億6500万円もの被害額となったジャパンライフ事件があります。「腰の具合が良くなる」という触れ込みの磁気ベルトを「購入後、他の人に貸せば運用利益が出る」と告げ、高額の支払いを受けた後に購入後のベルトを預かっていました。
しかし実際には、預かっていたベルト2万2,441点のうち、第三者にレンタルしていたのは2,749個。購入者が受け取っていた運用益は、レンタル料からくる利益ではなく、自分たちが支払ったお金の一部でした。これは典型的なポンジ・スキームの手口といえます。
また、栃木県にある安愚楽牧場(あぐらぼくじょう)は、「母牛に出資してオーナーになれば、毎年生まれる子牛の売却代金として3~8%の配当がある」という触れ込みでオーナーを募集。しかし繁殖牛の契約頭数は、実際の数を大きく上回っていました。つまり、架空の繁殖牛を販売していました。
自転車操業の安愚楽牧場はスキームが回らなくなり、破綻に追い込まれました。被害額は実に4,200億円にのぼり、日本史上最大の詐欺被害と言われています。
投資詐欺の被害状況
直近の詐欺被害状況はどのようになっているのでしょうか。金融庁によると、2024年1月1日から3月31日までに受け付けた「詐欺的な投資勧誘に関する情報」は2,355件。年齢が分かる情報提供者のうち、最も多いのが50代、次点で60代、次が70代という状況です。シニア層が狙われていることが分かります。
受付件数は、2021年10月~12月分の1,808件から547件の増加。これらが全てポンジ・スキームであるというわけではありませんが、被害に遭う人は確実に増えてきているといえます。
参考:「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:令和6年1月1日~同年3月31日)金融庁
ポンジ・スキームの見分け方
投資の初心者にとって、詐欺かどうかを見分けるのは困難です。しかしポンジ・スキームには共通した特徴があります。次の6つのポイントを確認し、詐欺的な投資話かどうかを判断しましょう。
「金融庁からの委託機関です」などと説明する
金融庁などの公的機関が、投資の勧誘等を民間業者に委託、指示することはありません。「認可」「許可」「指示」などの言葉にも気をつけましょう。
公的機関を連想させる名称を使用している
「こちらは●●●取引委員会です」「●●●センターです」など、公的機関であるかのような名称を使っている場合も要注意です。名刺をもらったら、必ずどんな事業者なのか、ウェブサイトなどで調べてみましょう。
「必ず儲かる」と言う
必ず儲かる投資話はありません。当然あるべきリスクについて触れない事業者は要注意です。
複数の業者から代わる代わる投資話がある
例えば、A社から投資の勧誘を受けた後、ちょうどB社からも連絡があり、「その株を勧誘されたのですか。それは見込みのある株です。良かったらウチで取引しませんか」などと言われたら要注意です。A社とB社は、実は同じ会社であり、投資話の信憑性を高めるため芝居を打っている可能性があります。
「未公開株です」と言う
未公開株とは上場していない株のことで、証券取引所で自由に売買ができません。幅広い投資家に未公開株を勧誘することは、一般的には考えられません。
金融庁の登録が確認できない
幅広い投資家に対して投資の勧誘ができるのは、金融庁(財務局)の登録を受けている業者だけです。
ポンジ・スキーム以外の投資詐欺
投資詐欺の手口は、近年のスマホ普及等により多様化しています。主に以下のような手口があるため、注意しましょう。なお、各手口は、ポンジ・スキームと組み合わせて詐欺となることがあります。
マルチ商法
マルチ商法とは、商品やサービスを契約し、次は自分が買い手を探して販売組織に加入させることで紹介料等を得るものです。この紹介システムで、会員数はピラミッド式に拡大します。マルチ商法は法律上「連鎖販売取引」と呼ばれ、クーリング・オフの対象となっています。
マルチ商法は、販売組織の会員となっても成果を上げられない場合、高額な商品をローンで購入した借金が残ってしまったり、自らが勧誘することで加害者となってしまったりする可能性があります。
情報商材詐欺
情報商材詐欺とは、インターネットの通信販売などで「儲かるためのノウハウ教えます」などの触れ込みで高額な商材を購入させる詐欺です。最近では、「副業で稼ぐために」と高額な教材やマニュアルを購入させ、実際には購入金の元をとれるような副業を紹介しないといった事例が目立ちます。
SNS型投資詐欺
LINEやインスタグラム、フェイスブックに代表されるSNSを通して行われる詐欺を、SNS詐欺と呼びます。具体的には、SNS上に表示された投資関連の広告をタップするとチャットメッセージが届きマルチ商法に誘われる、著名人と自称する者とチャットをやりとりして資金をだまし取られるなど、顔の見えないやりとりで巧みに誘導されるケースが増えています。
また、SNSなど非対面での連絡手段でやりとりすることにより恋愛感情を抱かせ、金銭等をだまし取る「ロマンス詐欺」も問題になっています。
セミナー型投資詐欺
セミナー型投資詐欺とは、投資セミナーを開いて参加者に高額な商材やコンサルティングサービスを購入させる手口です。参加者の中にはサクラがおり、セミナーを大いに盛り上げて他の参加者の感情をあおることがあります。
ポンジ・スキームや投資詐欺にあった場合の対処方法
万が一、ポンジ・スキームや他の投資詐欺にあってしまった場合の対処方法として、相談先や問合せ先を紹介します。
詐欺的な投資に関する相談ダイヤル(金融庁)
投資詐欺専門の相談ダイヤルです。損害を被った場合に限らず、詐欺的な投資勧誘を受けて不審に思った人や、投資を悩んでいる人などからの相談も受け付けています。相談の上、他機関の紹介や論点整理などのアドバイスをしてくれます。ただし、個別取引について斡旋や仲介、調停は行っていません。
電話(平日10時~17時)、ウェブサイトでの受付を行っています。
参考: 「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」の開設について(金融庁)
警察相談専用窓口
犯罪や事故に当たるのか分からないケースについて、悩み事や困りごとを相談したいときには「#9110」番を利用すれば、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口に繋がります。関係部署が連携して対応し、指導や助言、相手方への警告、検挙いった不安解消のための措置を講じてくれます。また、他のふさわしい窓口に案内してくれることもあります。
消費者ホットライン
「188」に電話すれば、居住地の近くの消費生活センターや消費生活相談窓口に繋がります。相談できる曜日や時間帯は、居住地の相談窓口によって違うため、まずは「188」に発信し、アナウンスに従って郵便番号を入力し、地域を選択しましょう。
ただ、市区町村の窓口が開所していない場合は都道府県の消費生活センターが案内されるや土日祝日は国民生活センターで相談の補完をするなど、原則として毎日利用が可能です(12月29日~1月3日を除く)。
参考:消費者ホットラインの概要[PDF:625KB](消費者庁)
未公開株通報専用窓口
未公開株・社債などを騙った詐欺についての相談を受け付けてくれるコールセンターです。フリーダイヤルは「0120-344-999」で、「上場確実」「あなただけに特別に譲渡します」など怪しい文句で勧誘してくる者について相談を承っています。
参考:未公開株通報専用コールセンターにご相談ください。(日本証券業協会)
まとめ
ポンジ・スキームの詐欺話に乗ってしまえば、最初は順調に配当が支払われていてもある日突然、相手方の企業と音信不通になる可能性があります。もし契約後に「詐欺ではないか」と気づいたら、契約書類を調べクーリング・オフ期間であれば速やかに解約の手続きを取りましょう。
クーリング・オフ期間を過ぎていたり、そもそも契約書にクーリング・オフに関する記述がなかったり、相手方が解約を渋ったりするようであれば、すぐ相談窓口への問い合わせをおすすめします。