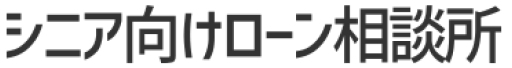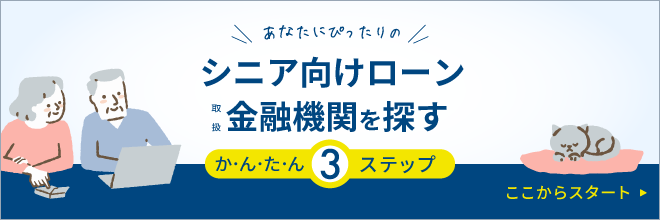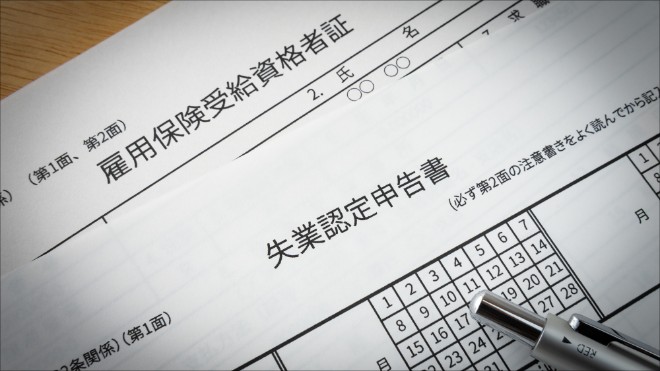65歳以上で年金を受給しながらパート収入を得る場合、扶養控除や社会保険の壁、所得税の課税ラインなど複雑な制度が絡みます。年金所得は雑所得として扱われ、公的年金控除が適用される一方、パート収入には給与所得控除が認められます。在職老齢年金制度による減額リスクや、扶養判定における合算所得の注意点も重要です。本記事では、年金受給者が扶養内で働くための控除や制度のポイントを、FPがわかりやすく解説します。
65歳以上の年金受給者の所得計算―年金所得控除と雑所得
年金とパート収入はそれぞれ異なる控除が適用され、合計所得の計算に影響します。それぞれ詳しく解説します。
公的年金控除の仕組みと65歳以上の控除額
65歳以上の年金受給者には、公的年金控除として最低110万円が認められています。例えば、年金収入が120万円の場合、控除後の所得は10万円となります。控除額は年金収入等の金額によって変動し、詳しくは以下の表の通りです。
【公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後、65歳以上)
|
年齢区分 |
年金収入額区分A |
公的年金等に係る雑所得の算出式(所得金額) |
|
65歳以上 |
〜329万9,999円 |
A-110万円 |
|
330万〜409万9,999円 |
A×0.75-27万5,000円 |
|
|
410万〜769万9,999円 |
A×0.85-68万5,000円 |
|
|
770万〜999万9,999円 |
A×0.95-145万5,000円 |
|
|
1,000万円以上 |
A-195万5,000円 |
パート収入(給与所得)の扱い(給与所得控除など)
パート収入は給与所得として扱われ、最低65万円(令和7年分以降)の給与所得控除が適用されます。たとえば、年間収入が123万円なら、控除後の所得は58万円となり、扶養判定の基準に影響します。控除額は収入に応じて変動しますが、65万円が最低ラインです。
扶養(税制上の扶養・配偶者控除)になるための目安ライン
税制上の扶養に入るには、年金とパート収入の合算所得が一定以下である必要があります。以下、シミュレーションを含めて詳しく解説します。
扶養・配偶者控除が適用される所得要件
税制上の扶養控除や配偶者控除は、令和7年分以降、合計所得金額が58万円以下であることが条件です。これは収入額ではなく、控除後の所得金額で判断されます。
65歳以上の場合、年金収入と給与収入の控除を差し引いた後の合算が58万円以下であれば、扶養対象となります。
年金所得+給与所得の合算で「扶養範囲内」に収めるには
65歳以上の場合、年金控除110万円と給与控除65万円を差し引いた後の所得が58万円以下である必要があります。控除後の所得がマイナスになる場合はゼロとして扱われ、相殺はできません。正確な計算が扶養維持のポイントです。
事例シミュレーション
父(67歳)の年金収入が120万円、パート収入が113万円の場合、税金の対象となる所得額の計算は以下のようになります。
公的年金:120万円-110万円(公的年金控除額)=10万円
給与:113万円-65万円(給与所得控除)=48万円
控除後の所得は年金10万円+給与48万円=58万円となり、扶養範囲内です。
逆に、例えば年金が80万円でも、給与が150万円の場合、年金控除後はゼロ、給与所得控除を引いた後の所得は85万円となり、扶養から外れます。このように、控除の扱い方次第で結果が変わるため、注意が必要です。
在職老齢年金制度と年金の減額リスク
働きながら年金を受給する場合、在職老齢年金制度によって年金が減額される可能性があります。どういうことか、いくら減額される可能性があるのか、具体的に解説します。
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金制度とは、年金受給者に一定の収入がある場合、年金の一部または全部が支給停止される制度です。対象は厚生年金加入者で、年金と給与の合計が基準額を超えると減額されます。
65歳以上に適用されるルールと基準額
65歳以上の場合、加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額と、給与の合計が月51万円(令和7年度。この基準額は毎年見直される可能性があるため、最新情報の確認が必要です)を超えると、在職老齢年金の支給が一部停止されます。
報酬比例部分の月額と給与の合計が基準額を超える場合、年金支給月額は以下の計算の通りになります。
基本月額※1―(基本月額+総報酬月額相当額※2―51万円)÷2
※1基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
※2総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
減額を避ける働き方・収入調整のポイント
年金減額を避けるには、月収を51万円以下に抑えることが大事です。パート勤務の時間や時給を調整することで、基準額を超えないようにする工夫が求められます。自らの基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)は、毎年6月頃に送付される年金額改定通知書に記載されています。年金額改定通知書が見当たらない場合は、年金事務所に問い合わせてみましょう。
社会保険(健康保険等)の扶養における条件
社会保険の扶養判定は、収入ベースで行われます。収入基準や、65歳以上の社会保険の加入の仕方などについて解説します。
健康保険の扶養になるための収入基準
60歳以上の年金受給者が社会保険の扶養に入るには、原則として年金と給与の合計収入が180万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である必要があります。これは、控除前の収入額で判定されます。月収ベースでは15万円未満が目安です。
75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行し、扶養の対象外となります。
年金受給中の医療制度
75歳以上になると、健康保険から後期高齢者医療制度に自動的に移行します。保険料は年金から天引きされることが多く、社会保険の扶養の概念は適用されません。ただし、税法上の扶養に入ることは可能です。扶養となることで、所得税や住民税が軽減されます。
70歳到達前後の厚生年金加入の扱い
70歳未満であれば、厚生年金に加入することが可能ですが、70歳到達後は厚生年金の加入義務がなくなり、保険料の支払いも不要になります。
ただし、法律上、70歳以上でも希望すれば厚生年金に任意加入できる場合があります。企業によって、また、入っている厚生年金や企業年金によって、加入条件や加入の可否が違います。
税金・確定申告・住民税の注意点
年金とパート収入がある場合、確定申告や住民税の扱いに注意が必要です。どんな場合に確定申告が必要になるか、非課税のラインはどこかについて解説します。
年金受給者+パート収入の確定申告は必要?
年金受給者は特に、確定申告不要制度が使える場合があります。次の2つに当てはまる場合、計算上は納税額が発生する場合でも、確定申告は必要ありません。
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
※1公的年金等:公的年金の他、企業年金など
※2公的年金等に係る雑所得以外の所得:生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
つまり、年金収入だけを見れば確定申告が不要でも、他にパート収入がある場合は、確定申告が必要になる場合があります。また、住宅ローン控除や医療費控除、災害や盗難に遭った場合に使える雑損控除を利用したい場合も、確定申告が必要です。
住民税の非課税ラインは自治体によって違う
住民税の非課税ライン(住民税がかからない所得金額)は自治体によって異なります。基本的な考え方は全国共通ですが、均等割(定額部分)があるかないか、扶養控除や障害者控除の扱いなどが、自治体によって微妙に異なるためです。
一般的には、年金やパート年収などを合わせた合計所得が一定以下であれば非課税になります。住民税が非課税であるかどうかは、扶養判定や医療費助成の割合、国民健康保険料の金額などにも影響するため、事前に自治体へ確認することが重要です。
まとめ
65歳以上で年金を受給しながらパート収入を得る場合、税制上、そして社会保険上の扶養判定に注意しなければなりません。在職老齢年金制度による減額リスクや、健康保険の扶養条件、確定申告の要否など、複数の制度をよく確認しましょう。制度の最新情報を確認しながら、安心して働ける環境を整えるのが大事です。