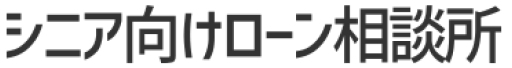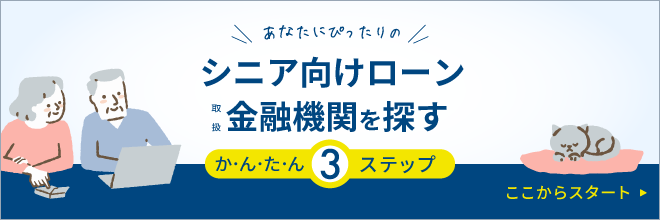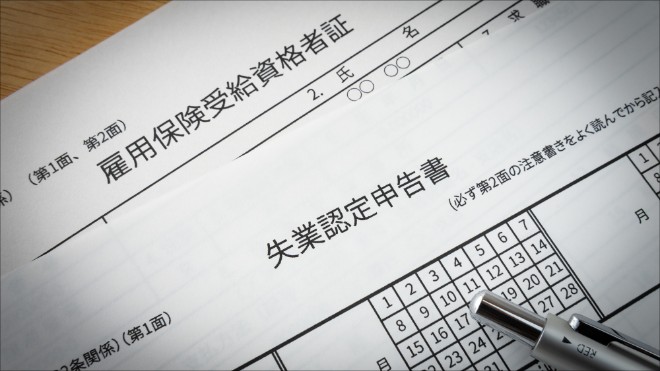社会人一年目は、慣れない仕事をする中で家計をやりくりしなければならない時期ですが、一人暮らしの方も実家暮らしの方も、無理なく貯金を始めることが重要です。平均貯金額や手取りを踏まえ、毎月無理なく貯金を増やしていけるコツや、今後の貯金プラン0円からのスタートでも目標を立て、今後のため少しずつ資産を形成していきましょう。
社会人一年目に貯金が重要な理由
社会人一年目は何かと物入りで、生活費や交際費など新しい出費が重なります。しかし、この時期に貯金の習慣を作ることで、生活基盤を安定させ、将来への備えを無理なく整えることができます。社会人一年目に貯金が重要な理由を、具体的に解説します。
生活基盤の安定と将来への備え
社会人一年目に貯金を始めることで、貯金を前提とした生活づくりの基盤ができます。手取り収入の一部を毎月積み立てるだけでも、半年後には一定の貯金が作れるので、生活に余裕が生まれます。この余裕を当たり前と感じることが大事です。貯金をするのが当たり前の生活が続けば、「毎月、あればあるだけ使う」といった金銭感覚に危機感を覚えるようになり、自然と貯金の癖がつきます。
また、若い社会人には、今後さまざまな人生のイベントが控えています。結婚、出産、マイホームの購入などに備えるためにも、早くから貯金を行うことは意味があります。
急な出費や転職リスクに備える
例えば1ヶ月につき2万円を貯金に回せば、半年後には12万円の貯蓄ができます。友人の結婚などがあっても、しっかりお祝いを包むことが可能です。このように急な出費にも慌てず対応することが可能になります。
また、転職を考えたとき、貯金があればすぐ行動に移せます。いざというとき、短期間なら無職でも暮らせる貯金があることは、精神的な安心感を生み出します。
信用情報やキャリア形成にも影響
若いうちからの貯金習慣は、ローンやクレジットカードの審査、住宅購入時など、信用情報にも良い影響を与えます。さらに、自分の収支を管理する力は、キャリア形成や社会人としての自立力にも直結します。
貯金を通じて、計画的な判断力や責任感を養うことができ、長期的な資産形成の土台を築けるといえるでしょう。
社会人一年目の平均貯金額はどのくらいか
「自分は貯金が少ない」と焦る人もいますが、まずは平均値や中央値を把握することが重要です。統計を見ると、若年層の貯金額は幅がありますが、無理のない範囲で少額から始めてみましょう。
平均と中央値の違いを理解する
貯金額についての統計を見る前に、まずは、「平均」と「中央値」の違いを理解しましょう。
貯金額の統計には平均値と中央値があります。平均値は、全体の平均を表しているため、高額貯金者の影響を受けやすいといえます。一方で中央値は、中間層の実態を示すため、実際に皆がどれだけ貯金しているかを見るのに便利といえるでしょう。自分の貯金が少ないからと焦らず、中央値を参考に計画を立てることが大切です。
年齢別・新社会人層の貯金データ
金融経済教育推進機構が継続して行っている「家計の金融行動に関する世論調査」より、年代別の貯金事情を知ることができます。2024年の調査では、以下のような結果となりました。
【年代別の平均金融資産保有額※】
|
年代 |
平均金額 |
中央値 |
|
20歳代 |
212万円 |
26万円 |
|
30歳代 |
604万円 |
140万円 |
|
40歳代 |
929万円 |
200万円 |
|
50歳代 |
1,147万円 |
200万円 |
|
60歳代 |
1,929万円 |
550万円 |
|
70歳代 |
1,830万円 |
650万円 |
※金融資産保有額…預貯金だけでなく、保険、個人年金、債券、株式、投資信託等も含めた金融資産の全体額
出典:家計の金融行動に関する世論調査(2024年)総世帯各種分類別データ
社会人一年目を含む20歳代では、金融資産保有額の平均額は212万円ですが、中央値が26万円です。つまり全体を平均すると212万円となるものの、実際には26万円ほどの金融資産しかない人が多いです。
また、金融資産を「非保有」(つまり貯金なし)と回答した人は、20歳代では33.3%に上ります。3人に1人が「貯金がない」状態です。
自分の貯金額が少なくても焦る必要はない理由
社会人一年目は、給与によるやりくりや生活リズムに慣れていない時期であり、貯金額が少なくても焦る必要はありません。そもそも手取りが少ないため、まだまだ親など上の世代からのサポートが必要な時期という考え方も根強くあります。貯金の習慣を作るのは、これからです。
社会人一年目でもできる貯金の仕組みづくり
無理なく貯金を続けるには、貯金の自動化と支出管理がポイントです。給与天引きや自動積立を活用し、固定費を削減することで、自然に資産形成ができます。また、キャッシュレス決済や家計簿アプリを活用することで支出を可視化し、無駄を減らせます。
給与天引き・自動積立の活用
給与口座から毎月一定額を自動的に別口座に移すことで、貯金を「使えないお金」として、目の前から消すことができます。少額でも毎月積み立てることで、半年後にはまとまった資金が形成されるでしょう。手動で貯めるよりも、心理的負担も少なく、貯金習慣が身につきやすい方法です。財形貯蓄制度を採用している会社であれば、給与天引きも活用しましょう。
固定費削減のポイント
社会人一年目は、生活費の中でも家賃その他の固定費が大きな負担になります。家賃については、契約更新のタイミングでより安く気に入った物件に移れるよう、常に不動産情報を収集しておきましょう。
なお、格安スマホや光熱費プランの見直しなどを行えば、小さな削減でも年間で数万円以上の貯金につながります。情報の比較はかなりの時間を要するため敬遠しがちですが、通勤時間などを利用して根気よく調べてみましょう。
キャッシュレスや家計簿アプリで支出管理
キャッシュレス決済や家計簿アプリを利用すると、支出の流れが見える化されます。どこに無駄があるか把握でき、予算内で生活する習慣が身につくため、おすすめです。
アプリをしっかり使いこなせば、自動記録やグラフ表示により、毎月の支出比較や貯金額の目標達成度も一目で確認できます。貯金に対してのモチベーション維持にも効果的です。
いくら貯めるべき?目標額の立て方
目標を持つことで貯金の習慣化がしやすくなりますが、無理な設定は禁物。挫折につながるかもしれません。貯金額は、現実的な範囲で設定しましょう。
初年度の現実的な貯金目標
目安の1つとして、一般的に「貯金額は給与の10~20%を目処にすると良い」と言われています。初任給が20万円だとしたら、2~4万円を貯金に回すということです。
給与の10~20%の貯金が現実的なラインであるか否かは、ライフスタイルや家庭の事情にもよります。実家暮らしなら余裕があっても、一人暮らしや、家の暮らしを支えるため仕送りをしている人などには厳しい金額と思えるかもしれません。
無理な高額を目標にすると生活が苦しく、挫折の原因になります。まずは無理のない範囲で、「毎月一定額を自動積立」と心得ましょう。少額でも、貯金額がだんだん大きくなっていくという経験が、貯金への自信を育むためです。
毎月積み立てられるのが少額過ぎて不安であれば、ボーナスなどの臨時収入を活用して貯金を増やすのがおすすめです。
3年目・5年目までのステップアップ目安
貯金額は、給与の増加に応じてステップアップさせるのがおすすめです。給与が上がったら、可能であれば上がった分だけ毎月の積立金額をアップさせましょう。「それではモチベーションが上がらない」と思うようであれば、給与が上がった分の半分を目安にするのもいい方法です。
昇給額は会社の状況や個人への評価によって違いますが、平均的な昇給率は4~5%と言われています。初任給が20万円であれば、年ごとに1万円ずつ上がっていく可能性も大いにあります。
初任給が20万円で、毎年1万円ずつ昇給し、昇給した分の50%を貯金に回すと設定して貯金額をシミュレーションしましょう。
【初任給の10%を貯金に回す場合】
1年目:毎月2万円ずつ貯金(年間24万円)
2年目:毎月2万5,000円ずつ貯金(年間30万円)
3年目:毎月3万円ずつ貯金(年間36万円)
4年目:毎月3万5,000円ずつ貯金(年間42万円)
5年目:毎月4万円ずつ貯金(年間48万円)
5年間の合計貯金額:180万円
無理な目標設定が挫折を招く理由
高すぎる貯金目標は、日常生活を圧迫しストレスにつながります。ストレスから高価な買い物をしてしまうと、貯金習慣自体が崩れてしまうでしょう。貯金をする自信をなくし、挫折してしまいかねません。
最初は少額でも確実に積み立て、成功体験を積むことで、モチベーションを維持しながら無理なく資産を増やすことが可能です。
将来の資産形成を見据えた行動
社会人一年目の貯金は、将来の資産形成への第一歩です。貯金の習慣がついたなら、少額からでも投資信託やつみたてNISAを活用し、投資の基礎知識を体験から得てみてはいかがでしょうか。また、社会保険や企業型DCなどの制度を理解し、老後資金を見据えた貯蓄行動を身につけましょう。
少額からでもできる投資信託・つみたてNISA
投資信託やつみたてNISAは、少額から資産形成を始められる手段です。「元本割れの可能性があるから、投資は不安」という人もいるでしょう。もちろん、投資には元本割れのリスクがつきものです。しかし、長期で投資をすると価格変動リスクが平均化され、複利効果も十分に得られるため、早くから投資を始めることが良いといえます。詳しく説明しましょう。
株式や投資信託は、1日や1か月といった短期スパンでは景気やニュースの影響で大きく上下することがあります。しかし多くの国や企業は経済成長を続けているため、数年、10年といった長期スパンで見ると、成長のトレンドにのる確率が高まります。
また、投資で得た利益を再投資すると、元本+利益に対してさらに利息や運用益がつきます。これを長期で繰り返すと、雪だるま式に資産が増えていくことになります。短期だとこの効果は小さいと言わざるを得ません。
毎月1万円程度の投資でも、長期で見ると複利効果で資産が増える可能性があります。貯金だけでなく投資を組み合わせることで、資産形成の幅が広がります。
社会保険や企業型DCなど制度を理解する
健康保険や厚生年金、企業型確定拠出年金(DC)など、社会人が利用できる制度を理解することも重要です。給与天引きで積み立てられる制度を活用すれば、自動的に資産形成が進みます。
健康保険や厚生年金は単に「引かれるお金」と思われがちですが、これらは将来の医療や年金を支える重要な仕組みです。老後の年金を形成するだけでなく、急な病気やケガ、産休中でも給与の3分の2ほどが保証されたり、障害を負ったり、死亡した場合の家族への保障制度もカバーしています。
また、勤務先によっては、企業型確定拠出年金(DC)に加入できる場合もあります。これは会社が掛金を拠出し、従業員自身が投資商品を選んで運用する制度で、掛金が非課税となるため節税効果も期待できます。
これらの制度は、意識しなくても給与天引きによって自動的に積み立てが進むのが大きな特徴です。自分の強い意志や管理がなくても「知らぬ間に資産形成が進む」仕組みを活用できるのは、会社員の大きなメリットといえます。
貯金と投資のバランスを取る方法
投資は元本割れのリスクを伴うため、あくまで余剰資金で始めるのが基本です。まずは最低でも3ヶ月分の生活費を貯金で確保しましょう。もしも転職したくなった場合、自己都合退職だと2~3ヶ月の待機期間があり、その間は失業給付が受けられないためです。
また、貯金は短期の緊急資金、投資は中長期の資産形成と位置付けるとバランスが取りやすくなります。「この先、長く手をつけない」と決まっているお金を、投資に回すのが賢い方法です。
まとめ
社会人一年目の貯金は、額の多さよりも「習慣化」こそが最大のポイントです。少額でも自動積立を実践することで、着実に貯金に対する自信がつき、将来への安心につながります。
今は生活に余裕がなくても、今後の昇給やボーナスを活かして少しずつ積み増せば大丈夫。焦らず、自分のペースで続ける仕組みを持つことが、長期的な資産形成の第一歩となります。